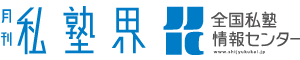優等生だった自分。
それに疑問を抱いたとき、
目の前の「窓」は開かれた。
学力という、唯一にして
画一的な価値観に踊らされる
親子を助けたい。
英会話には、そんな力がある。
パイオニア ランゲッジスクール(神奈川県)
マネージャー 中村 由香里さん
レールを外れてみたかった

マネージャー 中村 由香里さん
飛行機が空に残した一筋の白い雲は、彼女の夢が描いた軌跡そのものだ――三年生になったとき、その女子高生は単身渡米した。これから、一年間の留学生活の幕開けである。
ただ、留学とはいっても、高校が用意した交換プログラムの類ではない。渡米も、滞在先も通う学校も、すべて自ら(と家族)が独力で判断・手配したものだ。「ずっと敷かれたレールの上を歩んできて、そこを外れてみたかったんだと思います」。当時を回顧して、当人・中村由香里はそう笑う。
地元の有名私立校に通い、勉強が得意で生徒会長も務める「ザ・優等生」だった中村。目指している大学もあったが、ふと感じた。「これって、本当に私がやりたいことなのかな……」。
テストで良い点を取ることだけが、唯一の存在証明であり人間的価値。志望校に挙げた大学も、特にそこへ行きたかったわけではなく、立場上そのあたりが妥当だろうと空気を読んだだけだ。
そう、彼女は自分の人生ではなく、日本社会が望む理想的高校生の人生を生きようとしていた。演じている自分に気づいてしまったのだ。
母の背中を追って

母で校長の祐子さん。中村さん共々、熱い教育理念の持ち主だ
そこに気づける感性を彼女に授けたのは、間違いなく母だ。約三五年前、母の祐子は、静岡・富士宮で小さな英会話スクールを開いた。現在、中村がマネージャーを務める『パイオニアランゲッジスクール』の前身だ。とはいえ、当時はただでさえ英会話スクールなど珍しかった時代。ましてや静岡の片田舎となれば尚更である(現在は神奈川へ移転)。
しかも母自身、英語に堪能だったわけではないという。彼女は大学で心理学を学んだが、学会で外国の研究者と意思疎通すらできない自分たち日本人に、猛烈な危機感を抱いたのが始まりだ。それは単に語学力だけの問題ではなく、外国人とコンタクトを取ろうとする意思そのもの、最も原始的なコミュニケーション力の欠如と言っていい。「こんな状況は私たちで終わりにしたい。次の世代に、英会話力という新しい窓を創ってあげたい」。それが開校の理由だった。
経営者であり、妻であり、親であり、同時に祖父の介護まで行いながら自分の情熱を次々と形にしていく母への憧れ……母は信念の人であり、明らかに自分の人生を生きていた。その有形無形のイズムは長い年月をかけて中村のなかに種を蒔き、やがて彼女が一八歳を迎えるころ一気に芽吹くこととなる。
決められた物差しの中で、さまよう親子たち

校長・スタッフのみなさんと。創業時はネイティブ講師を自宅に下宿させていたほどだという
海を渡った中村に、自由の大地は次々と価値観のシャワーを浴びせてくれた。中でも驚いたのは教育哲学だ。
個人主義のアメリカでは、不得意な科目があってもそれを「劣る」とは見なさず、個性だと考える。代わりに得意なことをとことん認め、伸ばす教育だ。また、いま学力がふるわない子でも、学びへの熱意や努力の過程が評価されれば大学へも進学でき、奨学金も得られる。子供の未来に賭け、評価し、投資する発想なのだ。
対して日本は、得意を伸ばすよりも、苦手をなくして平均化することが是とされる。「今の」成績が悪ければ次の学びの門は決して開かれない。日本式教育の利点も理解できるが、子供の価値をはかる物差しが学力しかないのはどうなのか。さらに、親も子もそれが正しいと信じ込まされ、成績だ受験だと踊らされ、疲弊を重ねている。そんな思考停止的社会に恐怖すら感じた。彼らを救い出してあげたい、そうじゃないよと教えてあげたい……中村のなかに理念が生まれた瞬間だった。
やがて米国の大学を卒業して帰国。大手塾などで働いたのち、母の教室へ。夢は大きく「日本人の開放」である。母は英会話力を「窓」と称したが、その気持ちは同じだ。英語を通じて世界に繋がれば、視野の裾野は無限に広がる。学力=人間的価値という一方通行の一本道を歩いてきた子供たちに、「どこにだって歩き出せるんだ」と気づかせてあげたい。それが中村の、『パイオニア』たる彼女の、教育フロンティアだ。(敬称略)
文/松見敬彦
中村 由香里 YUKARI NAKAMURA

静岡県出身。英会話スクールを経営する両親のもとで育ち、留学を経て日本の教育の画一性に疑問を抱く。大手の塾企業・通信事業企業に勤めたのち、両親が興した『パイオニアランゲッジスクール』入社。受験英語ではなく英会話というスタンスを貫き、単なる語学力としてのそれではない、総合的・人間的コミュニケーション力を伸ばすことに力を注ぐ。
●WEBサイト
http://www.pls-edu.jp