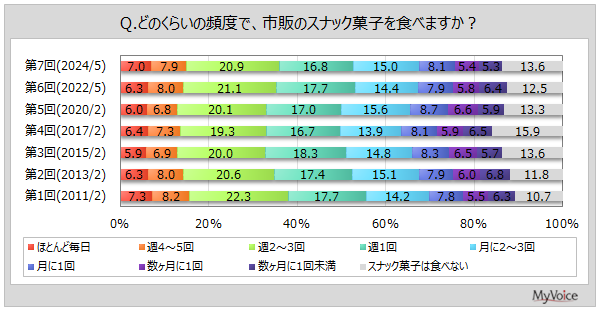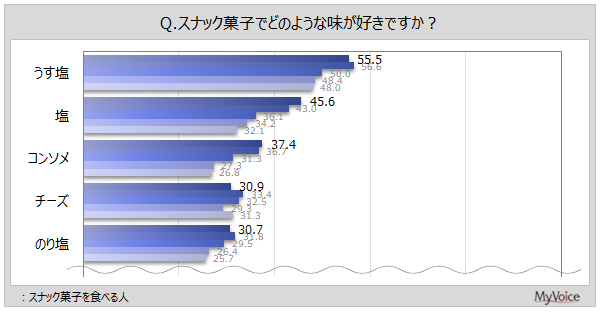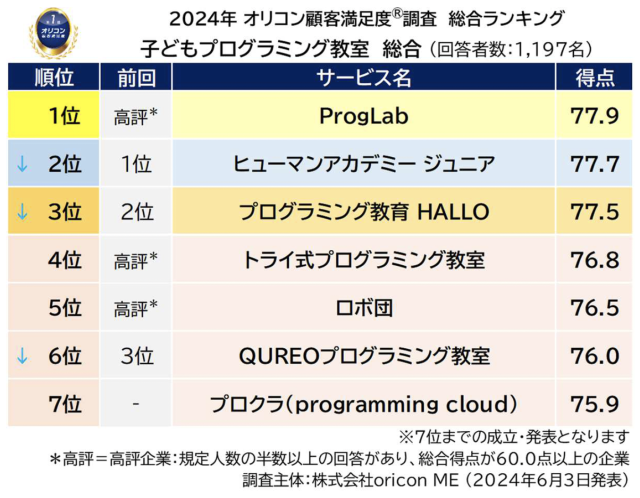個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン(東京・新宿区、山下 一仁 代表取締役社長)は、中学生の子どもを持つ全国の保護者1,000名を対象に、「中学生の夏休みの過ごし方に関する実態調査」を実施した。
「中学生の夏休みの過ごし方に関する実態調査」結果概要
結果概要 ①
・保護者の約半数が夏休み期間中、子どもにストレスを感じている
・夏休みの子どもに対するストレスの原因、最多回答は「長時間のスマホ・ゲームの使用」
結果概要 ②
・中学生の夏休みの予定、第1位「部活・クラブ活動」、第2位「家族旅行」
・夏休みに保護者が子どもに望むこと、最多回答は「規則正しい生活リズムを守ること」
・夏休みの宿題に生成AI使用はOK? 中学生保護者の4割以上は否定的
結果概要 ③
・中学生の半数以上が計画通りに夏休みを過ごせていない/計画を立てていない
・保護者の6割以上が子どもは夏休みを有意義に過ごしていると回答
・夏休みを有意義に過ごせなかった理由、最多回答は「計画性がなかった(38.4%)」
【Topics】あなたは夏休みの期間中、お子さまに対してストレスを感じることはありますか?(n=1,000、単一回答方式)
保護者の約半数が夏休み期間中、子どもにストレスを感じている
中学生の子どもを持つ全国の保護者1,000名を対象に、夏休み期間中、子どもに対してストレスを感じることがあるか質問したところ、48.4%が「ストレスを感じる」(ストレスを感じる:15.2%、どちらかというとストレスを感じる:33.2%)と回答した。
Q1 あなたは何に対してストレスを感じていますか?(n=484、複数回答方式)
夏休みの子どもに対するストレスの原因、最多回答は「長時間のスマホ・ゲームの使用」
また、夏休み期間中、子どもにストレスを感じていると回答した保護者484名を対象に、ストレスを感じる原因について質問をしたところ、最多回答は「長時間のスマホ・ゲームの使用(46.7%)」、次に「生活リズムの乱れ(44.8%)」、「食事の準備や片付け(44.0%)」と続いた。
Q2 お子さまの今年の夏休みの予定についてお答えください。(n=1,000、複数回答方式)
中学生の夏休みの予定、第1位「部活・クラブ活動」、第2位「家族旅行」、第3位「塾の夏期講習」
子どもの夏休みの予定について質問したところ、最多回答は「部活・クラブ活動(41.2%)」、次に「家族旅行(32.7%)」、「塾の夏期講習(25.0%)」と続いた。
Q3 今年の夏休みお子さまに生活面で望むことは何ですか?(n=1,000、複数回答方式)
夏休みに保護者が子どもに望むこと、最多回答は「規則正しい生活リズムを守ること」
夏休みの期間中、生活面で子どもに望むことについて質問したところ、最多回答は「規則正しい生活リズムを守ること(56.4%)」、次に「計画を立て過ごすこと(45.2%)」、「スマホやTVゲームの使用時間を控えること(36.4%)」と続いた。
Q4 夏休みの宿題や課題に生成AIを使用することについてどのように思いますか?(n=1,000、単一回答方式)
夏休みの宿題に生成AI使用はOK? 中学生保護者の4割以上は否定的
子どもが夏休みの宿題や課題に生成AIを使用することについてどのように思うか質問したところ、30.2%が「使用するべきだと思う(使用するべきだと思う:7.7%、どちらかというと使用するべきだと思う:22.5%)」、41.0%が「使用を控えるべきだと思う」(使用を控えるべきだと思う:21.6%、どちらかというと使用を控えるべきだと思う:19.4%)と回答した。また、28.8%が「わからない」と回答した。
Q5 あなたのお子さまの夏休みの過ごし方としてあてはまるものをお選びください。(n=1,000、単一回答方式)
中学生の半数以上が計画通りに夏休みを過ごせていない/計画を立てていない
次に、昨年の夏休みの過ごし方について、子どもが計画通りに過ごしたか質問したところ、38.1%が「計画通りに過ごしている」(計画通りに過ごしている:7.5%、どちらかというと計画通りに過ごしている:30.6%)と回答しました。一方で、37.2%が「計画通りに過ごしていない」(計画通りに過ごしていない:14.6%、どちらかというと計画通りに過ごしていない:22.6%)、17.8%が「計画を立てていない」と回答、合わせると中学生の半数以上が計画通りに夏休みを過ごせていないか、計画を立てていないことがわかった。
Q6 あなたから見てお子さまは昨年の夏休みを有意義に過ごしたと思いますか?(n=1,000、単一回答方式)
保護者の6割以上が子どもは夏休みを有意義に過ごしていると回答
昨年の夏休みの過ごし方について、子どもは有意義に過ごしたと思うか質問したところ、62.5%が「有意義に過ごしたと思う」(有意義に過ごしたと思う:17.9%、どちらかというと有意義に過ごしたと思う:44.6%)、26.3%が「有意義に過ごしていないと思う」(有意義に過ごしていないと思う:10.2%、どちらかとういうと有意義に過ごしていないと思う:16.1%)と回答した。
Q7 あなたから見て有意義でなかったと思う理由をお答えください。(n=263、複数回答方式)
夏休みを有意義に過ごせなかった理由、最多回答は「計画性がなかった」
昨年の夏休み、子どもは有意義に過ごしていないと回答した保護者263名を対象に、子どもの夏休みが有意義でなかった理由について質問したところ、最多回答は「計画性がなかった(38.4%)」、次に「生活リズムが乱れていた(36.5%)」、「日々、長時間スマホをしていた(36.5%)」が並んだ。
<調査概要>
有効回答数 中学生の子どもを持つ全国の保護者1,000名
調査期間 2024年6月3日~2024年6月8日
調査方法 インターネットリサーチ調べ