秋田県は、11月にタイに教員2人を派遣し現地で授業。来年1月には高校生16人を派遣する。タイから教員や学生も呼び込み交流の経験を積み、他の東南アジア諸国にも広げる。県では「探求型」として実績のある授業を世界的な教育方式に育てたい考えだ。秋田県は全国学力・学習状況調査で2007年度の1回目以降、全国トップレベルを維持する。好成績を下支えしているのが独自の「探求型授業」。児童や生徒が(1)自分たちで課題を設定し(2)話し合いながら解決方法を探り(3)学習内容を振り返る――という授業スタイルだ。
株式会社iTEP Japan(東京都新宿区)は3月27日、E−CAT(English Conversational Ability Test)の説明会と受験体験会を開催した。E−CATとは新しく開発された英語スピーキングテストのことで、アメリカロサンゼルスに本社を置くBES(Boston Educational Services)が開発。発案者は、文科省の委員も務める英語講師の安河内哲也氏だ。

安河内氏の説明に聞き入る参加者たち
E−CATを受験する際は、ヘッドセットとマイクを装着してインターネットに接続されたパソコンに向かい、指示に従いながらインタラクティブに発話していく。発話した音声データはインターネット経由でアメリカに送られ、トレーニングを受けたアメリカの採点者によって採点される。
テストはパート1〜パート6に分かれていて、パート1は自分のことを話す「自己紹介」、パート2は英文をクリアに読めるかどうかを試す「音読」、パート3は身近なトピックに関して答える「トピック」、パート4は表示される2枚の写真に関して答える「写真描写」、パート5は画面上のドキュメントについて答える「資料」、パート6は自分の意見を述べる「意思表明」となっている。

E-CATのコンセプトを語る安河内哲也氏
E−CATは現行のスピーキングテストの弱点を克服すべく、様々な工夫がされているのが特徴だ。その1つとして挙げられるのが、発話を誘導するガイド(静止画像)の存在である。ガイドは優しい口調で語りかけてくれ、テストの緊張をほぐしてくれる。BESと試行錯誤しながらE−CATを開発した安河内氏は「これまでのスピーキングテストのような、いかにもテストという雰囲気を改善し、リラックスして受験できるようにしたかった」と話す。
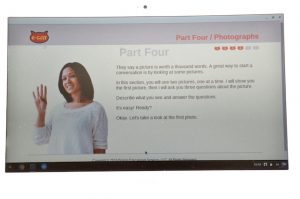
やさしいガイドにより緊張せずにテストを進められる
また、問題が出題されてから答える間に練習時間を設けるなど、受験者が普段の力を発揮しやすいようにしている他、アカデミックやビジネスなどのような専門領域は扱わず、誰でも経験したことがあるジェネラルな問いが出題されるようになっている。このことによって、英語が得意な中学生をはじめ、高校生、大学生、社会人等すべての人が対象となる。さらに、問題は乱数で自動生成され、近くの受験者とは異なるものを出題。受験者同士が同じ問いに答えることで不正が起こる、といったことがないよう配慮するなど、細部にまでこだわってつくられている。

実際のテストを体験する参加者たち
CEFRでいうA1〜B2レベルの能力が測定できるこのテストの受験方法と受験料は、「団体受験」が4500円、「公開受験」が6000円、「個人受験」が7000円となっていて、日本を代表する複数の大企業がすでに団体受験の申し込みをし、試験を実施し始めているという。また、どんなパソコンからでも自由に受験できる、準公式版もリリースされる予定である。
安河内氏は「E−CATは、学校や企業での英語教育によい影響を与えられることを目指しており、今後大きなテストに育てていきたい」と抱負を語っている。E−CATに関する問い合わせは、電話03・3513・4511(iTEP Japan)へ。
文部科学省は4月4日、全国の公立中学・高校の生徒の英語力に関する2015年度調査の結果を発表した。都道府県別の状況が初めて公表され、中3で実用英語技能検定(英検)3級程度以上の力があるとされた生徒の割合は最高の千葉(52.1%)、秋田48.6%、東京47.9%と続いた。一方、高知25.8%、熊本26.9%など8道府県が30%を下回った。高3は同様に英検準2級程度以上の力がある生徒の割合を調査。最も高かったのは群馬の49.4%。ほかに千葉45.5%、福井42.5%などが高く、沖縄21.8%、和歌山22.5%などが低かった。
全国平均は3級程度以上の中3生の割合が36.6%(前年度34.6%)、準2級程度以上の高3生の割合が34.3%(同31.9%)で、ともに年々向上している。もっとも、政府は17年度までに中学卒業段階で3級程度以上、高校卒業段階で準2級程度以上の割合をそれぞれ50%にする目標を掲げており、達成は厳し状況だ。