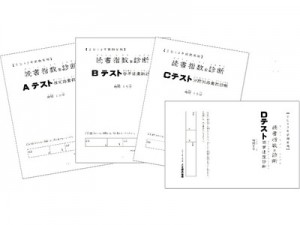読書は、国語力を伸ばすのはもちろん、たくさんの語彙を習得して思考力を高めるためにもとても大切なことだ。しかし、スマホやテレビゲームなどの誘惑が多く、子供たちの読書量は減少している。では、どうすれば子供たちが読書をするようになるのだろうか? その解決方法のひとつとなるのが、株式会社理究によって開発・提供されている学習システム「ことばの学校」だ。
読書は、国語力を伸ばすのはもちろん、たくさんの語彙を習得して思考力を高めるためにもとても大切なことだ。しかし、スマホやテレビゲームなどの誘惑が多く、子供たちの読書量は減少している。では、どうすれば子供たちが読書をするようになるのだろうか? その解決方法のひとつとなるのが、株式会社理究によって開発・提供されている学習システム「ことばの学校」だ。
その特徴は、「良書多読」「速聴読」「読書ワーク(語彙)」「読書ワーク(読解力)」「読書指数診断」の5つのメソッドで構成された「読むとくメソッド」というプログラムにある。
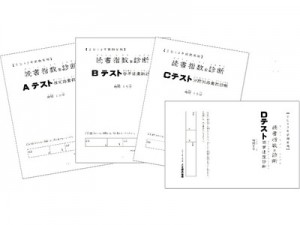
読書指数診断
まず、名作や入試問題によく出題される作品などの「良書」が、学齢に合わせリスト分けして提供されるため、選書に迷うことなく多読できるようになっている(「良書多読」)。また、パソコンを使い、その「良書」を朗読音声で聞きながら読むことにより、集中して読書ができるようになっているだけでなく、朗読音声のスピードも上げることができ、同時に読書スピードを上げる訓練もできるようになっている。そして、音声はおよそ30ページ(約20分)ごとに区切られているため、無理なく、また集中力が散漫になることなく読み進めることができ、自分のペースで楽しみながら読書速度を高めていけるよう工夫されている(「速聴読」)。そして、読書の前後に語彙や読解力の確認を行い(「読書ワーク」)、培われた「語彙力」と「読書速度」を、「読書指数診断」で客観的な国語力として測定できる。
このように「ことばの学校」は、読書をすることにとどまらず、読んだ本の中から自然に語彙や言葉の運用法を身につけることができ、読解力を自然に高められるように設計されている。
「ことばの学校」は、小学校入学前から中学生まで3つのコースが用意されている。段階に合わせ、読書を通した学習ができるためカリキュラムにも組み込みやすい。

あざみ野個別学習塾で開催された「ことばの学校」体験型セミナーの様子
あざみ野個別学習塾(横浜市青葉区)の野田和孝塾長によると「小学生に入塾してもらうきっかけになった」といい、保護者からも「子供が家で読書をするようになった」と喜ばれているという。
5月8日に体験型セミナーがおこなわれる国語道場(千葉市稲毛区)では、国語以外の教科も指導しているが、国語力がすべての学力に通じるという考えから「ことばの学校」を導入し、それに合わせ塾名も変えた。これにより、塾長の教育理念をしっかりと伝えることができるようになり、「ことばの学校」を軸に近隣の塾とも明確な差別化を図ることができた。
また、公立中高一貫校をはじめとして、今後増えていくとみられる適性検査型入試にも対応できるのも「ことばの学校」の強みだ。5月20日のセミナー会場となっている自由塾町屋教室(東京・荒川区)では、その特色を生かし、新規開校のメインコンテンツとして導入した。
「ことばの学校」を塾経営にどう活かしているか実際に現場で体験し、経営者同士で情報交換もできる体験型セミナーは5月〜6月にかけて随時開催されている。「読書感想文対策講座」など、夏休みに向けた新たな講座立ち上げにも参考となる。各会場3組まで、と限られた人数で開催される「ことばの学校」体験型セミナーの詳細と申し込みはことばの学校専用サイトへ。
<PR>