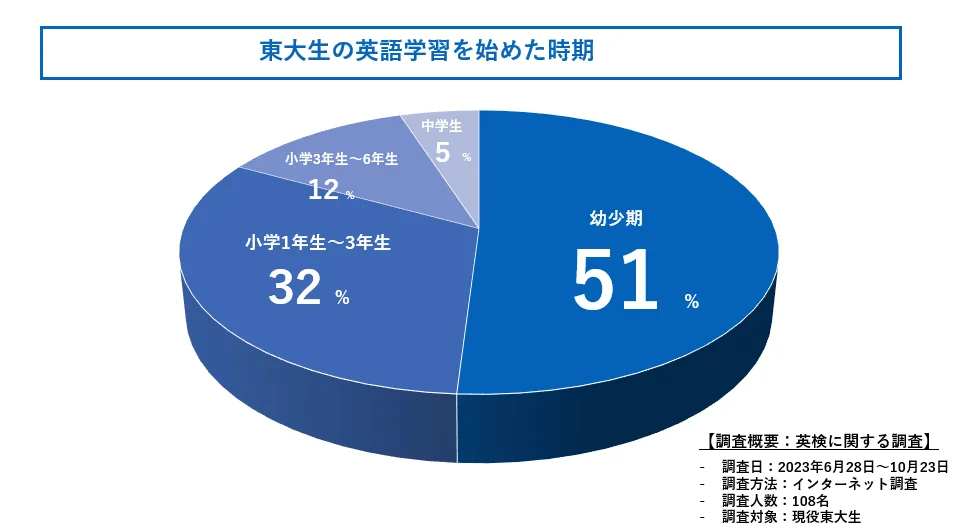認定特定非営利活動法人カタリバ(東京・杉並区、今村久美 代表理事)は、日本全国の教育支援団体や学校と連携し、実践型探究学習「全国高校生マイプロジェクト」の推進に取り組んでいる。2023年12月から2024年1月にかけて、各学校で生徒たちの探究学習をサポートしている高校教員340名を対象に、探究学習に感じている課題などについてのアンケート調査を実施した。
必修化から2年経ち、探究を推進する組織の設置は8割超
2022年度から高等学校では「総合的な探究の時間」が必修科目となり、そこから2年の月日が経過した。今回のアンケート調査では、探究学習に取り組む学校の82%が探究学習カリキュラムの企画や開発、推進を統括する組織が校内に設置されていると回答。探究学習の推進を組織的に行おうと試みる学校がある程度増えてきたことがわかった。
一方で依然9割超が「課題を感じている」結果に。特に「授業案やカリキュラムの設計」「調べ学習で終わってしまう」などが課題
校内組織が設置されている学校であっても、教職員間の思いや認識に差がある等、運用についての課題感を挙げる声も多く寄せられている。前述のように、学校の中で探究学習を推進する組織が出来たとしても、探究学習の推進を担当している教員や生徒伴走にあたっている教員の約92%が、探究学習の推進に関して「課題を感じている」と回答した(「とても感じている」「まあ感じている」の合計)。
課題だと感じていることの具体例としては「授業案やカリキュラムの設計」「調べ学習で終わってしまう」「校内で探究学習への理解が広がらない」への回答が多く見られた。
また、自由記述の欄では以下のような声が上がった。
▼回答した教員の声(一部抜粋)
・教職員間における探究学習に対する指導の考え方が異なったり、熱量に差があったりする
・探究活動について他の校務分掌と揉めることがある
・少数の意識の高い教員がやっているだけの状態
外部人材の活用や探究学習を推進する風土がある学校ほど、教員の課題感が低い傾向
今回の調査では、「コーディネーターなど外部人材の配置」、「活動の浸透や文化づくりを目指した校内風土の醸成」の2つの取り組みが進んでいる学校において、教員の課題感が低い傾向にあることがわかった。
コーディネーターの配置は35%ほどだが、配置している学校ほど教員の課題感がやや低い傾向にあり、特に、コーディネーターが配置されていない学校と比べて、強い課題感を感じている教員の割合は約17%少ないことがわかった。一方、コーディネーターが配置されていない学校の教員は、「とても感じている」と答えた割合が51%、「まあ感じている」と答えた割合が43%で、より多くの教員が探究学習における課題を感じている可能性がある。
また、探究学習の表彰や活動の掲示など、活動の浸透や文化づくりを目指した「校内風土の醸成」に取り組んでいるほど、教員の課題感が低く、探究学習を進めやすい傾向にあることも明らかに。外部の人材の活用、校内全体で探究学習の推進に取り組む風土が重要であるという傾向が見えてきた。
このような課題を解決すべく、カタリバはこの度全国の高等学校を対象に「総合的な探究の時間」のカリキュラム開発研修「探究スタートアップラボ」の参加校を募集している。
年3回の対面研修を中心とした年間を通じた伴走プログラム。大きな特徴として、以下の3つが挙げられる。
①各校3名程度のチームで参加し、自走できる組織的な推進を目指す
②先進校フィールドワークを通じて、知見やノウハウを効率的に学ぶ
③アクションプランを自校に持ち帰り、実際に改善実践に取り組む
▼詳細は以下のページへ
https://myprojects.jp/news/18788/
▼資料請求・説明会申込はこちら
https://forms.gle/rvWukYr3jTAXsRed7
調査概要
調査テーマ:探究学習の推進における課題
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査地域:日本全国
対象者:全国高校生マイプロジェクトを自校で推進した全国の教員340名
実施期間:2023年12月13日~2024年1月31日