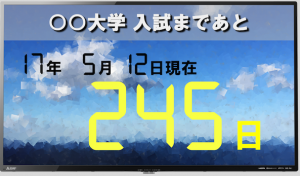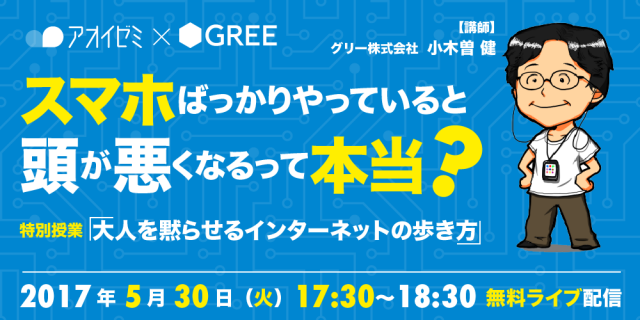デジタルハリウッド佐藤昌宏氏
ニュートンジャパン株式会社が主催する「教育分野での人工知能・AI活用! 注目のテクノロジーアダプティブ・ラーニング」が3月29日、都内で開催された。基調講演を行なったデジタルハリウッド大学大学院教授の佐藤昌宏氏は、「テクノロジーは、制度や仕組みを形骸化する側面がある」と語る。教育においては、ラーナーセントリック(学習者中心の学習モデル)の加速により、個人、学習者が先行しているとも。その上で、異業種の取り組みを紹介。その一つに『habit(ハビット)』のサービスを挙げる。

Classi株式会社の加藤理啓副社長
このサービスは、遺伝子解析のキットを用いて、個人の遺伝子情報に基づいた食事が届けられるアダプティブなサービス。その食事は、無機質なサプリメントではなく、エンターテイメント性に富んだ食事であることに注目し、教育とテクノロジーを結びつけていくヒントになるのではないかと述べた。
Knewton(ニュートン)のプロダクトを採用した日本の先進事例も紹介された。Classi株式会社の加藤理啓副社長は、「学習支援プラットフォームClassi」によるアダプティブラーニングの実践事例を紹介し、アダプティブラーニングによって学校での学習の質の変化が語られた。

学研塾ホールディングス木本充氏
株式会社学研塾ホールディングス・経営企画本部の木本充シニアディレクターは、「自立型個別学習G-PAPILS」を紹介。ニュートンの技術を使った学習アナリティックス・教材レコメンデーション機能に加えて、感情面のサポートをする「メンター」を配置したことを特長として挙げた。目標や学力レベルが異なる受講者に人に、最適な助言や励ましを行うことで、学習の継続に必要なモチベーションの維持を担う。首都大学東京と共同開発したメンタリングメソッドのデータに基づいたサポートのため、メンターの質も高い水準を維持し、〝自立型個別学習〟を推進する。

株式会社Z会の草郷雅幸氏
株式会社Z会・ICT事業部の草郷雅幸部長は、「英語4技能講座」、「代数(数や式)」、「幾何(図形)」、「解析(関数や微積分)」、「統計」の4領域から学ぶ「数学新系統講座」など先進的なアダプティブラーニングを提供する、「21世紀型Online Academy Z会 Asteria」を紹介。無学年制(中学生〜社会人を推奨)で、学習指導要領にとらわれない新たな学習サービスだ。

パネルディスカッションの様子
当日は、佐藤氏のモデレートのもと、Knewton Inc.のライアン・プリチャードCEOは、「我々のデータドリブン(収集したデータを元に次のアクションを起こす型)型のプラットフォームを利用することで、コンテンツプロバイダーはコンテンツの制作に集中できる」と語り、Knewtonのサービス、機能を語った。その上で、「どういう生徒に使われたかをプロバイダーと共有して良いものができる」と続け、「学校・塾現場でのアダプティブラーニングの現状と展望」についてパネルディスカッションが行われた。

佐藤氏とライアン氏の対談の様子